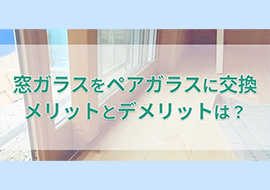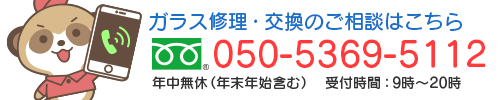窓ガラスの防犯フィルムの選び方から施工方法、効果まで

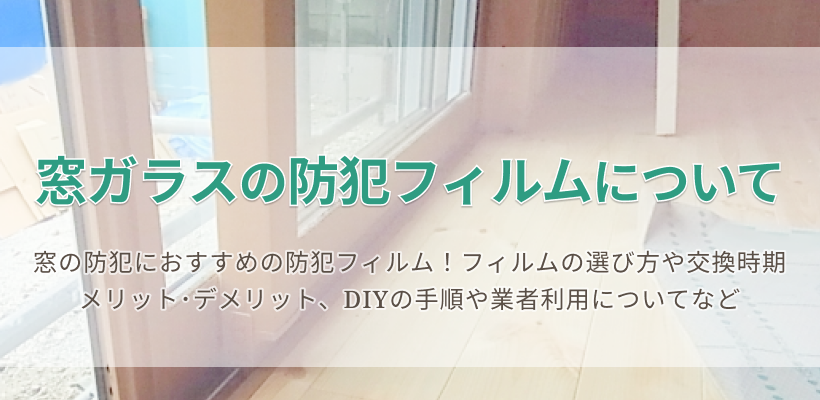
窓ガラスの防犯フィルムを徹底解説
近年、空き巣や侵入窃盗などの犯罪が増加しており、住宅のセキュリティ対策がますます重要視されています。その中でも、窓ガラスへの対策は、空き巣の侵入経路となることが多く、特に注目されています。窓ガラスに防犯フィルムを貼ることは、手軽に高レベルのセキュリティ対策を実現できる方法の一つです。
本記事では、窓ガラスの防犯フィルムについて、その種類や選び方、施工方法、効果、そして費用まで、網羅的に解説します。防犯フィルムを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
防犯フィルムとは?
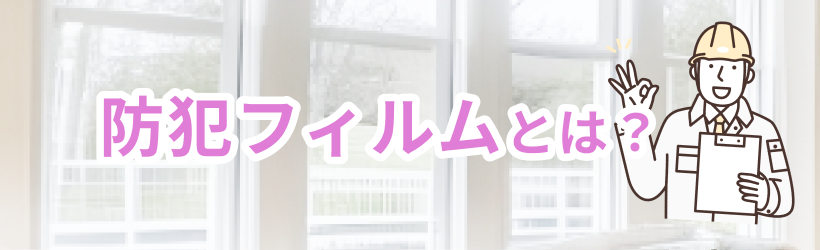
防犯フィルムとは、窓ガラスを割って室内に侵入者が押し入るのを防ぐ目的で使用される防犯アイテムです。
通常、ガラスは外部からの攻撃に弱い性質で、硬い物が強くぶつかったり、一点に集中した衝撃などを受けると簡単に割れてしまいます。
防犯フィルムにはガラスや金属への粘着性が非常に高い素材が用いられており、窓ガラスに貼っておくことで、もし窓が攻撃を受けてガラスが割れてしまっても、破片がフィルムに貼りつくため割れ落ちて穴が開くことを防止できるのです。
防犯フィルムは通常、複数の層で構成されており、特殊な接着剤で窓ガラスに貼り付けられます。
厚さや構造によって防犯性能が異なりますが、厚みが350㎛以上ある官民合同会議防犯認定品などの高性能な製品は391ミクロン以上の厚さを持つものが多いです。
空き巣が窓ガラスを破って侵入することを防ぎ、住宅を安全に守る効果があります。
窓の防犯が大切な理由
住宅への侵入犯罪において特に空き巣は、窓を侵入経路とする犯罪者の数が非常に多いことが統計で示されています。
警察庁が公表しているデータによると、住居への侵入窃盗の約63.4%が、窓から行われているとされているようです。
通常のガラスは耐衝撃性が低く簡単に割ることができるため、窓を侵入経路とする犯罪者は、窓ガラスを割ってから直接カギを開けてから、サッシを開けて室内に侵入しようとします。
そのため、防犯フィルムなどを貼って窓の防犯性能を向上させることは、住居への侵入犯罪を防止することに繋がるのです。
犯罪者が窓ガラスを割る方法とは
空き巣や居抜きなどを目的とした犯罪者が窓ガラスを割る方法には、「打ち破り」・「三角割り(こじ破り)」・「焼き破り」という3つの手法が用いられることが多いです。
「打ち破り」は、バールやバットやハンマーなどの武器によってガラスを強く打ち付けて割る方法です。
ガラスの破壊音が響いたり周囲の人に姿を見られたりすることなど、目立つことを躊躇しない乱暴な手段ですが、短時間で住居に侵入することができることから、貴重品の位置を把握されていたり、居住者に危害を加えることが目的の場合などで使用されることが多いとされています。
「三角割り(こじ破り)」は、マイナスドライバーなど小型かつ鋭利な道具を窓ガラスとサッシ枠の隙間に差し込んで、テコの原理を使って圧力をかけることでガラスを破壊する手法です。
窓のクレセント錠周辺のガラスを小さな範囲だけ割ることから、ガラスの破壊音も作業している姿も目立ちにくく、道具も小さいことから、空き巣が住居侵入にもっとも用いる方法であると言われていいます。
「焼き破り」はバーナーやターボライターなどで窓ガラスを強く熱した後に、冷水や瞬間冷却スプレーなどを当てて急冷することで熱割れ現象を引き起こし、窓ガラスを割る方法です。
一般的な住宅で用いられることの多いフロート板ガラスであれば、10秒程度熱して冷却すると簡単に割ることができてしまいます。
窓ガラスを短時間で破壊することができ、ガラスの破壊音がほとんどせず、道具が比較的コンパクトなどの理由から、侵入窃盗犯がガラス破りに使用する手段として選択することが多いと言われています。
防犯フィルムに使用される素材
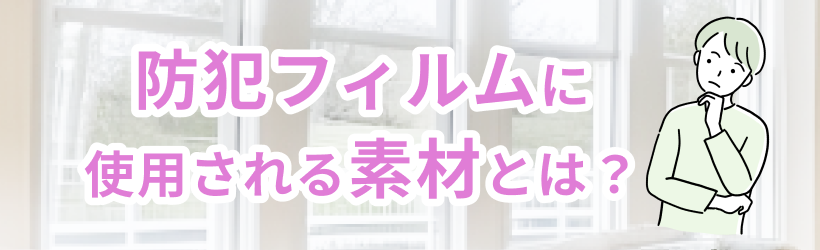
防犯フィルムには、主に以下の種類があります。
PET(ポリエチレンテレフタラート)
PET(ポリエチレンテレフタレート)はペットボトルにも使用される材質で、建築窓ガラス用フィルムの主要な素材となっています。
防犯フィルムには一般的にPETが使用されることが多く、典型的な防犯フィルムは複数層のPETフィルム(各0.1mm厚)を積層した構造になっています。
PETを用いた防犯フィルムは、強度が高く透明度も高いのが特徴です。
ポリカーボネート
ポリカーボネートが材質の防犯フィルムは、PET(ポリエチレンテレフタレート)に比べて強度が非常に高く、耐衝撃性に優れています。
ただしポリカーボネート製の防犯フィルムは熱膨張率がガラスの約7倍、PETフィルムの約5倍と非常に高く、温度変化が大きい窓に貼ると自然に剥離してしまう可能性があります。
例として、西日が強く当たってガラスの温度が上がりやすい窓や、日中と夜間で温度差が大きくなりやすい部屋の窓などに貼るには注意が必要となります。
防犯フィルムの効果・メリット
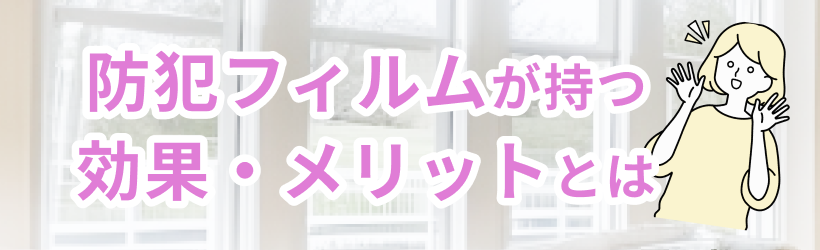
防犯フィルムを貼ることで、以下の効果・メリットが期待できます。
ガラス破りへの抵抗力向上
防犯フィルムを窓に貼ることで、ガラスが割れにくくなり、空き巣など犯罪者の侵入を困難にします。
目立つことを嫌う泥棒は、住宅に侵入する際に5分以上の時間がかかった場合、約7割が侵入を諦めると言われています。
防犯フィルムによって侵入の難易度が上がることから、犯罪抑止の効果が期待できるのです。
割れたガラスの飛散防止効果
防犯フィルムには「ガラスの破片の飛散防止効果」もあります。
窓に防犯フィルムが貼られていると、衝撃・攻撃を受けてガラスが割れても、破片がフィルムに粘着して飛び散るのを防いでくれます。
ガラスが割れるシーンは意外と多く、例えば台風や突風で飛んできた物が窓ガラスにぶつかって割れた、地震で窓がフレームごと歪んでガラスが割れた、小さいお子様が投げたオモチャが窓ガラスに激突した、めまいや立ちくらみで窓にもたれてしまい窓ガラスが割れたなど、様々な原因が予想されます。
防犯フィルムを窓ガラスに貼ることで、窓の防犯機能がアップするだけでなく、自然災害の発生時や、日常で起きるトラブルで窓ガラスが破損した場合にも、ケガのリスクを軽減することができるため安心です。
紫外線カット効果
防犯フィルムのほとんどの製品には、紫外線をカットする効果があります。
タンスやカーペットやベッドなどの家具、畳やフローリングほか建材などを紫外線から保護することができるため、日焼けや色あせを防いで長持ちさせることができます。
また、紫外線は人体にとっても有害です。
紫外線の種類のうち、UV-B(中波長紫外線)は窓ガラスに吸収される性質のため、窓を閉めていると室内に届くことはほとんどありません。
ですが、人体に悪影響を及ぼすUV-A(長波長紫外線)は、一般的な窓ガラスを通過することができます。
UV-Aは通称、「生活紫外線」と呼ばれており、季節や太陽の位置に関係なく年間を通して地表に届いており、皮膚の表皮を超えて真皮にまで達する性質を持っています。
UV-Aを長期的に浴びることで皮膚にダメージが蓄積されると、シミ・シワ・タルミなど肌の老化スピードを早めたり、皮膚がんの原因にもなったりします。
防犯フィルムは種類にもよりますが、紫外線のカット率が99%以上の製品が少なくないため、防犯フィルムを窓に貼ることで、副次的に紫外線カット効果を得られることがほとんどとなるのです。
遮熱性能の向上
防犯フィルムにはいくつか種類があり、中には遮熱性能を持った製品もございます。
遮熱機能付きの防犯フィルムを窓ガラスに貼ると、窓に当たる日差しを反射することで、室内に入る日射熱の量を低減させることができます。
夏のジリジリとした熱が室内に侵入することを防いでくれるため、クーラーの効きが良く快適に過ごせる手助けになるでしょう。
また、冬には室内の暖まった空気の温度が外に逃げることを防止することができます。
冷房や暖房など空調設備の効きが良くなり、高効率で稼働させることができることから、空調にかかる光熱費のカット効果や省エネ効果を期待することができます。
コストパフォーマンスに優れている
防犯フィルムは窓ガラスを防犯ガラスに交換するよりも、全体的な費用を抑えることができ、コストパフォーマンスに優れていると言えます。
既存の窓ガラスに貼るだけで使用することができるため、工事が比較的簡単で施工時間も短めのため、工事費が安く済みます。
ガラスそのものに防犯機能を持たせた防犯ガラスの場合、2枚のガラスの間に樹脂製の中間膜やポリカーボネート板などを挟み込んだ構造で、製造時には圧着・加熱といった加工が必要となるため工場でしか製造することができません。
防犯ガラスは性質上、現場でガラスをカットできないため基本的には受注生産となり、防犯ガラス1枚あたりの単価は高く、重量があるため工事にも人員が必要で作業時間も長くなってしまうのです。
一方、防犯フィルムは防犯ガラスに比べると商品単価が安く、窓のサイズに合わせてカットが可能ですので、現場で切り出すことができます。
コストパフォーマンスを重視して窓に防犯機能を持たせるのであれば、防犯フィルムがおすすめです。
視界を遮らない
防犯フィルムは一般的に可視光線透過率が85%以上のため、日中は室内の明るさが十分に保たれます。
ガラスに防犯フィルムを貼ることで、部屋が暗くなってしまうのではないかと懸念される方もおられますが、可視光線透過率は50%以上あれば、暗さはほとんど感じられないとされています。
また、防犯フィルムは透明性が高いため、視界を妨げたり開放感が損なわれる心配もありません。
防犯フィルムを窓ガラスに貼る際の注意点・デメリット
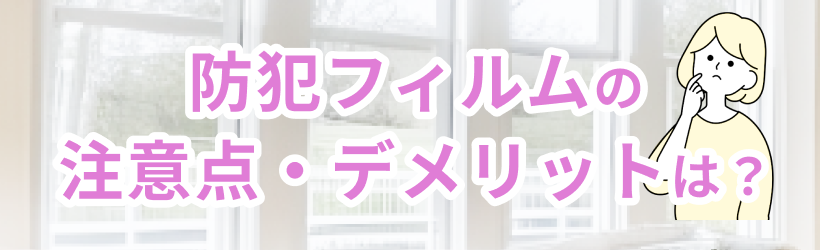
様々な効果やメリットが期待できる防犯フィルムですが、使用するうえでの注意点やデメリットもあります。
防犯フィルムを貼ったあとで後悔しないように、デメリットについてもしっかり把握しておきましょう。
耐用年数が短い
防犯フィルムは約10〜15年で劣化し、貼り換えが必要になります。
防犯ガラスの耐用年数が約20年以上であるのに対し、フィルムは半分程度の寿命しかありません。
長期間使用していると、時間の経過とともに防犯フィルムが黄ばんでしまう、剥がれ・めくれが生じるなど、劣化が進んでしまいます。
フィルムが劣化すると見た目が悪くなってしまうだけでなく、防犯性能も低下することから、防犯フィルムは定期的に新しいものに貼り換える必要があると言えるでしょう。
施工が難しい
防犯フィルムを窓に貼り付けるには、専門的な技術や経験が必要です。
DIYによる防犯フィルムの貼り方はたくさんのホームページや動画サイトなどで紹介されており、一見すると簡単に貼ることができそうに思いますが、実際には取り扱いは簡単ではなく、失敗してから結局業者に依頼したという方も少なくありません。
自分で貼り付けることは可能で、業者に依頼しなければそのぶん工事費用がかからずコストを安く抑えることができますが、取り扱いに慣れていないと、接着面に気泡やゴミやホコリが入ってしまったり、フィルムに折れ目やシワができたりするなど、見た目がキレイに仕上がらない可能性があります。
また、窓ガラスと防犯フィルムの密着度が不十分な場合、ガラスへの粘着性が低下し防犯機能や破片の飛散防止機能が十分に発揮できない恐れもあります。
そのほか、フィルムのカットに失敗して買い直しになった、施工時に水抜きがきちんと行われておらず、施工後しばらくしてからフィルムにズレが生じてしまった、窓の開け閉めの振動が影響して剥がれてしまったなど、DIYによる失敗リスクは非常に多いのです。
プロに依頼した場合は、防犯フィルムが持つ機能を最大限発揮させることができ、仕上がりが美しく工事が短時間で済み、フィルムを長持ちさせることができます。
防犯フィルムの種類選定、必要なフィルムのサイズ計測や切り出し、貼り付け作業まですべて一括で対応してもらえるほか、もしもの時に安心のアフターフォローサービスも用意されているなど、業者を利用するメリットはたくさんあります。
そのため、DIYに自信がないのであれば、業者に依頼することをおすすめします。
養生期間中は強度が不十分
フィルム貼り付け直後の養生期間中は、フィルムの強度が十分に発揮されないため、効果が限定的になります。
防犯フィルムを窓ガラスに貼る際、専用の施工液を使用します。
この施工液がしっかり乾燥していない状況では、ガラスとフィルムの接着が甘く、本来備わっているはずの防犯機能や破片の飛散防止機能が十分に発揮できず強度が出ないのです。
施工液が完全に乾くのは、冬季であれば約1~3か月、冬季以外であれば約1か月程度と言われています。
その期間は、窓まわりの防犯には注意が必要になります。
防犯フィルムの選び方
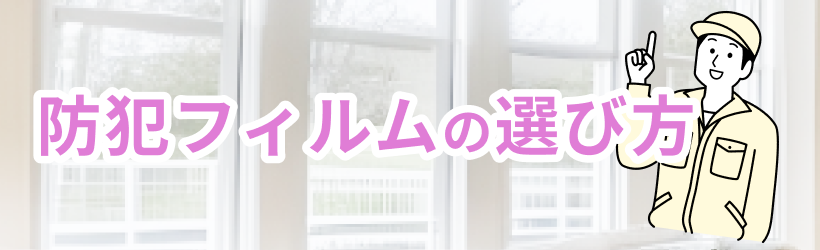
防犯フィルムを選ぶ際には、様々な要素を考慮する必要があります。
ご自宅の窓ガラスに最適な防犯フィルムを選ぶために、以下のポイントを参考にしましょう。
窓ガラスの種類に合わせてフィルムを選ぶ
窓に使われるガラスは、透明なフロート板ガラスだけでなく、黒いワイヤーが入っている網入りガラス、凹凸模様が入った型板ガラスや不透明なすりガラス、2枚以上のガラスが1セットとなっている複層ガラス(ペアガラス)や合わせガラスなど、様々な種類があります。
ガラス用のフィルムは、ガラスの種類によって貼れるタイプと貼り付けができないタイプがあるため、現在使用している窓ガラスの種類に合わせたフィルムを選ばなければなりません。
特に注意しなければならないのは網入りガラスと複合ガラス(ペアガラス)で、相性の良くないフィルムを貼ってしまうと日射熱を過度に吸収してしまい、熱割れを起こす可能性がございます。
ガラス屋や窓用ガラスフィルム専門店に依頼すると適切なフィルムを選んでもらえますが、DIY作業によって自分で防犯フィルムを貼ることを検討されているようでしたら、ガラスの種類を確認し、貼り付け可能な防犯フィルムを選んで購入するようにしましょう。
市販の防犯フィルムでは、パッケージや説明書にフロート板ガラス専用、型板ガラス対応、網入りガラス対応など、どのガラスに使用することができるか記載されているため、簡単に確認することができます。
防犯フィルムの厚さ・強度を確認する
ガラスの強度を高めるためには、厚みのあるフィルムを選ぶことが重要です。
防犯フィルムは厚いほどガラスへの接着性が高く破れにくく、防犯性能が高くなります。
防犯フィルムの厚さは、一般的にミクロン単位で表されます。
350ミクロン以上の厚みがある防犯フィルムは、侵入者が窓を割るのに時間がかかるため、防犯効果が高いとされています。
注意点として、「飛散防止フィルム」には防犯機能も備わっていると間違われる方がいらっしゃるのですが、飛散防止フィルムは防犯フィルムほど強度が高くないため、防犯対策としての機能は不十分です。
特に、厚さが200ミクロン以下の防犯フィルムでは、強度が低いことから防犯グッズとしては性能が足りず、期待した防犯効果が得られないことが懸念されます。
防犯フィルムを選ぶ際は、「防犯」「防犯用」などの記載がされており、なおかつ十分な強度を持っている厚みのある製品を選ぶことをおすすめいたします。
防犯性能の証明がある製品か確認する
防犯フィルムの商品選びでは、防犯性能が証明された製品を選ぶことも重要です。
「CPマーク」が付与されている製品は、一定の防犯性能基準を満たしており、侵入に5分以上かかることが確認されています。
そのため、窓の防犯レベルをより高めたいのであれば、CPマーク認定防犯フィルムを選定することをおすすめします。
「CPマーク」とは?
CPマークとは、防犯性能の高い建物部品に付けられるマークです。
「CP」は「CrimePrevention」の略で、日本語で防犯を意味します。
このマークは、警察庁、国土交通省、経済産業省、および民間関係団体で構成される「官民合同会議」が行う厳しい試験に合格し、住宅などへの侵入に5分以上耐えられると評価された部品に与えられます。
第三者機関によってその性能が評価されていることから、機能面についての信頼性は高いと言えるでしょう。
CPマークの対象となる建物部品には、鍵、玄関ドア、サッシ、ガラス、面格子など。
防犯フィルムもCPマークの認定商品として、対象となっています。
CPマークの貼付条件について
防犯フィルムのCPマーク貼り付けは、日本ウインドウ・フィルム工業会が規定している以下の条件を満たした場合に認められます。
・防犯フィルムの厚みが、350㎛以上である。
・日本ウインドウ・フィルム工業会によって指定されている接着剤が用いられている。
・防犯フィルムの貼り付け作業は、防犯フィルム施工技能者(国家検定技能士)によって施工される。
・厚さ5㎜以上のフロートガラス、または厚さ3㎜以上の複層ガラスに施工される。
・3㎜厚複層ガラスに施工できる製品は、性能評価試験に合格したものに限られる。
・防犯フィルムの施工は、防犯性能を確保するため窓ガラスの全面に貼り付ける「全面貼り」を行うこと。窓の一部分のみにフィルムを貼り付けを行う「部分貼り」は認められない。
価格帯で選ぶ
防犯フィルムの価格は、種類や厚さ、サイズによって大きく異なります。
予算に合わせて、最適な製品を選びましょう。
また、ガラス屋や窓ガラスフィルム専門業者に防犯フィルムの貼り付け作業を依頼する際は、フィルム代のほか、工事費や出張費など総合的な金額の比較も重要です。
防犯フィルムの貼り付け作業を業者に依頼した場合、一般的には「防犯フィルムの商品代、作業費、出張費」の合計が支払い金額となります。
ですが、フィルムの値段は窓の大きさやフィルムの種類によって異なりますし、狭所作業や高所作業など現場の環境、すでに貼ってあるフィルムを剥がす作業が必要となる場合など、状況によって料金は大きく変動します。
そのため、業者を利用する場合は、複数の業者に連絡して見積もりを取り、費用を比較することがおすすめです。
施工のしやすさを確認する
自分で施工する場合は、施工のしやすさも考慮しましょう。
最近では、作業に必要なヘラなどの道具がセットとなっていたり、専用の接着剤などを使わず水だけで貼り付けることができる無接着剤静電気付着タイプといった、初心者でも比較的簡単に貼り付け作業ができるように配慮されている防犯フィルムも多く販売されています。
また、商品によっては作業の手順が分かりやすい解説動画を用意している場合もございます。
自分で防犯フィルムを貼る場合は、慣れていないと失敗してしまうリスクがあることを考慮し、事前に施工のしやすさや施工できそうかを確認してから、フィルムを選ぶようにしましょう。
防犯フィルムの交換、貼り換えを行うタイミングは?
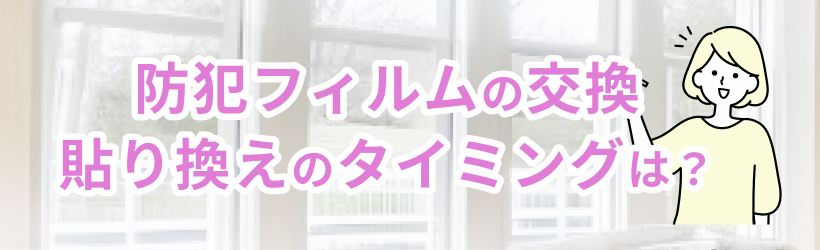
防犯フィルムは一般的に、10~15年程度を目安として交換・貼り換えを行うことが推奨されています。
劣化が進んだフィルムは防犯効果が低下し、見た目も悪くなってしまうため、早めの交換が必要です。
特にフィルムが乳白色に変化していたり、フィルムとガラスの接着面に気泡が発生していたりする、フィルムの端に剥がれ・めくれが生じているなど、外観に特徴的な変化がみられる場合は劣化が進行しているため早急に交換することをおすすめいたします。
また、熱がこもりやすい部屋の窓や、湿気の多い部屋の窓など、環境によっては10年未満でフィルムが劣化して貼り換えが必要となることも少なくありません。
劣化して見た目が悪くなっている防犯フィルムが貼られている窓を放置していると、空き巣などの犯罪者は防犯意識に欠けている家だと判断する可能性もあります。
そのため、防犯フィルムの劣化に気付いた時点、または10年を目安にして、定期的にフィルムを交換することもおすすめです。
防犯フィルムの施工方法
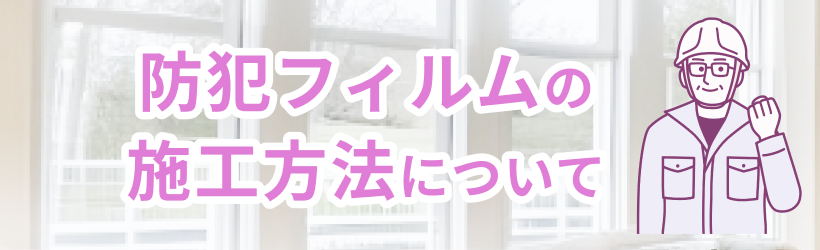
防犯フィルムの施工は、専門業者に依頼するのが一般的です。
ですが、最近ではDIYに対応した防犯フィルムが販売されており、入手が簡単かつ施工しやすい商品も増えていることから、ご自身で貼り付け作業を行う方も増えているようです。
DIYで施工する場合は、以下の手順で行います。
防犯フィルムの貼り方①下準備を行う
まずは、窓周辺の片付けや養生を行います。
防犯フィルムを窓ガラスに貼る際は、水または水溶液を使用するため、水で濡れると困るものはあらかじめ片づけておくようにしましょう。
カーテンやソファやタンスなどの家具はもちろん、空気清浄機やヒーターやテレビなどの家電製品などは、離れた場所に移動させておきます。
周辺の物を片づけたら、窓付近の壁や床などの養生を行います。
テープ付きの養生シートがあれば簡単ですが、無い場合はゴミ袋や不要なタオルなどで代用することができます。
また、コンセントの差込口が窓の近くにある場合は、ビニールで覆うように養生しておきましょう。
防犯フィルムの貼り方②窓ガラスをきれいに掃除する
ガラス表面に汚れやホコリが残っていると、フィルムがきれいに貼れません。
防犯フィルムとガラスの間に、ゴミやホコリなどが入り込んでしまうと、見た目が悪くなるだけでなく、貼り付けに失敗してフィルムを無駄にしてしまう可能性もございます。
また、ゴミが入ると空気も入るため、防犯フィルムが持つ本来の防犯性能を発揮できなくなる可能性もあるため、窓ガラスを事前にキレイに掃除するのは非常に重要です。
窓ガラスの清掃は、ガラス専用のクリーナーを使用するか、または食器用などの中性洗剤を混ぜた水を霧吹きで吹きかけて使用します。
洗浄液を窓ガラスに吹きかけたら、ガラス用のワイパーやゴム製のヘラなどを使ってガラス面をキレイにしましょう。
この時、タオルや雑巾など布は使用しないでください。
繊維や糸クズがガラス面に残ってしまうことを防ぐためです。
もしシールやガムテープの跡など、ガラスの表面に強固な汚れがこびりついているようでしたら、スクレーパーなどの道具を使用して落としてください。
防犯フィルムの貼り方③フィルムをカットする
貼り付ける窓ガラスのサイズに合わせて、防犯フィルムをカットします。
窓ガラスの縦と横の長さをメジャーなどで測ったあと、フィルムを約3cm程度を目安として、少し大きめにカットします。
やや大きめにカットしておくことで、作業時にフィルムのサイズ調整がしやすくなり、小さくカットしすぎることも防止できます。
防犯フィルムの切り取り作業は、カッターで行うことができます。
切り取る際には、フラットな場所にフィルムを置いてください。
凹凸が多い場所でフィルムをカットすると、折り目やシワ、傷などができるリスクがあるためです。
防犯フィルムの貼り方④貼り付け液を吹きかける
窓ガラスとフィルムの間に、貼り付け用の水溶液を塗布します。
水溶液は、水に中性洗剤を数滴ほど混ぜたもので代用できますが、購入された防犯フィルムに施工液が付属していたり、説明書に施工液の作り方が記載されているようでしたら、そちらに従ってください。
水溶液は、ガラス面にたっぷりと吹きかけましょう。
液の量が少なすぎると、フィルムを貼った後にズラしにくくなってしまい、位置の調整が難しくなるだけでなく、ズレた位置で接着剤が乾いて剥がれてしまい失敗する恐れがあります。
液の噴霧を行う際は、スプレーボトルや噴霧器などを使うと、液が均一にかかってムラができにくいためおすすめです。
防犯フィルムの貼り方⑤防犯フィルムを窓ガラスに貼り付ける
水溶液をガラスに吹き付けたら、すぐに防犯フィルムを貼る作業に移ります。
水溶液が乾いてしまったり垂れてムラができたりすると、フィルムがうまく貼りつかず失敗の原因となります。
防犯フィルムのリリースフィルムを剥がしたら、ガラスに合わせて防犯フィルムを貼り付けていきます。
ガラスの端からフィルムを貼り付け、空気が入らないように注意しながらゆっくりと平らになるよう広げます。
フィルムの上辺を軽く抑えて、フィルムの位置が均等になるように丁寧に貼り付けます。
もしフィルムの位置調整が必要になった場合や、施工液が不足しているようであれば、乾燥してフィルムが動かなくなる前に水溶液を足してください。
フィルムを端から少しだけ剥がしてから、隙間から水溶液を吹きかけながら、ゆっくりとフィルムを剥がすことで、位置を調整することができます。
防犯フィルムの貼り方⑥フィルムとガラスの間の空気を抜く
防犯フィルムの仮固定が終わったら、貼り終わったガラスの表面に水溶液をしっかりと吹きかけてから、ゴムベラやスキージーなどの道具を使って、窓ガラスと防犯フィルムの間に入っている空気と余分な水溶液を押し出します。
空気と水溶液を除去することで、防犯フィルムをしっかりと窓ガラスに密着させて接着性を高めることから、防犯効果や破片の飛散防止効果を最大限に発揮させることができます。
この作業を行う際のポイントは、必ず防犯フィルムの表面に水溶液を吹きかけることです。
ガラスと防犯フィルムの間に残っている空気の塊や水溶液を抜く際に、ゴムベラやスキージーを使用しますが、水溶液が吹きかけられていないとフィルムの表面にキズがついてしまう原因となります。
ゴムベラやスキージーは、窓ガラスの中心から端に向かって、上下方向と左右方向にゆっくりと動かしてください。
力加減にも注意が必要で、強く圧迫しすぎてしまうと、防犯フィルムにキズがついたりズレが生じたりする原因となります。
防犯フィルムの貼り方⑦余分なフィルムをカットする
窓ガラスと防犯フィルムの間に残っている空気や水溶液を抜く作業が終わったら、余分なフィルムをカットして窓の大きさに合わせます。
このとき、窓枠から約2mmほど内側に隙間ができるようにフィルムをカットしてください。
窓ガラスのサイズにピッタリ合うようにフィルムをカットしてしまうと、端に残っている空気や水溶液がうまく抜けなくなってしまいます。
カットするときは、フィルムの上から定規などを窓枠の少しだけ内側に当てて、カッターを使ってゆっくりと慎重にカットしてください。
また、一気に切り取ることは避けて、少しずつカットすることをおすすめします。
ゆっくり丁寧にカットすることで、ゆがみが生じずまっすぐに切り取ることができるため、仕上がりが美しくなり、ケガの防止にもつながります。
防犯フィルムの貼り方⑧仕上げに水溶液を再度抜く
仕上げとして、水溶液をもう一度防犯フィルムの表面に吹きかけてから、ゴムベラやスキージーを使ってしっかりと水抜きを行います。
押し出された水溶液は、スポンジやペーパーなどを使って吸い取っておきましょう。
水溶液が余分に残った状態になると、防犯フィルムがガラスにしっかりと貼りつかず剥がれやヨレの原因となるため、入念に水を抜いておく必要があります。
仕上げの水抜き作業が終わったら、作業完了です。
防犯フィルムを貼った後に注意すべきポイント
防犯フィルムを窓ガラスに貼った直後は、窓の透明度が若干下がったように感じることがあります。
この現象は、窓ガラスとフィルムの間に残った水溶液による影響で起きますが、水溶液は時間の経過とともに自然に蒸発しますので、無理に取り除く必要はありません。
通常は、1~2週間程度で残った水分は蒸発します。
窓の防犯フィルム貼り付けは専門業者への依頼がおすすめ
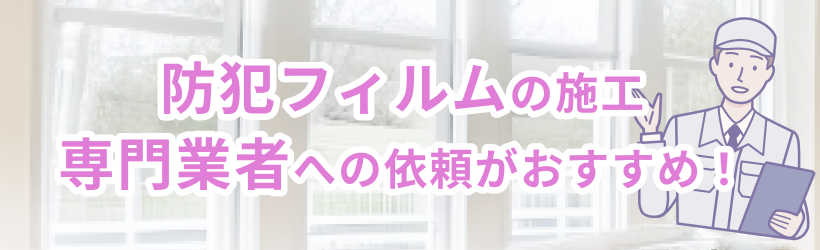
防犯フィルムの貼り付けは技術が必要で、慣れていないと時間がかかったり失敗したりする心配があります。
そのため、確実な防犯効果を得たい場合や、手間をかけたくない場合には、ガラス屋や窓ガラスフィルム専門の業者などプロに依頼することが望ましいです。
以下で、防犯フィルムの貼り付け作業を業者に依頼することで得られるメリットについて解説します。
専門的な技術による確実な施工
プロの技術で適切に防犯フィルムの貼り付け作業が行われるため、フィルムの密着度が高く、剥がれにくくなります。
特に、大型の窓や複雑な形状の場合は、作業が難しく自分で貼るのは難しいため、業者の利用がおすすめです。
DIY作業では慣れていないと見栄えが悪くなったり、防犯性能が最大限に発揮できない可能性があります。
また、自分で貼るよりスピーディかつ仕上がりがキレイになるというメリットもございます。
適切な製品選択
専門業者に相談すると、窓の状態や目的、希望する防犯レベル、予算などに合わせて、最適な防犯フィルムを提案してもらえます。
防犯フィルムには多種多様な製品があるため、状況に合わせて最適なフィルムを選ばなければなりません。
窓まわりの防犯レベルをとにかく高めたい、複層ガラス(ペアガラス)に貼れる防犯フィルムを提案してほしい、防犯機能だけでなく目隠し機能や遮熱機能などの追加機能も希望しているなど、豊富な商品知識を持ったプロに相談すれば、お客様の要望に合った防犯フィルムを提案してもらえます。
もしフィルムの種類選びで悩んでいる場合や、希望するフィルムが自宅の窓ガラスに適しているか分からない場合などは、専門業者に相談されることをおすすめいたします。
品質保証
業者による施工は通常保証付きで、不具合が生じた場合の対応が期待できます。
施工が原因による異変に気が付いた場合、業者の責任としてアフターフォローサービスを受けることができるため、もしものトラブルでも安心です。
例えば、通常使用下において、防犯フィルムの品質劣化が著しく、劣化や変色によって見た目が悪くなった、フィルムが剥離してしまったなどのトラブルでは、保証の対象となるでしょう。
ただし、自分でフィルムにキズをつけてしまったり、剥がしたりした場合は、保証の対象外となります。
また、ハイスペックな防犯フィルムの一部商品には、空き巣などの犯罪者が窓ガラスを割って部屋に侵入して被害が出た時に、お見舞金制度が給付される制度が用意されていますが、こちらは防犯フィルムの販売会社が請け負う保証となっています。
防犯フィルムの費用
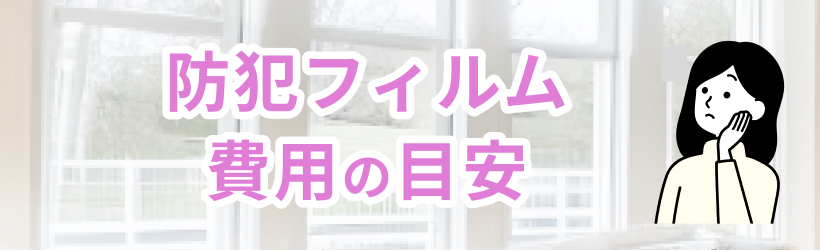
窓ガラス防犯フィルムを貼る際の費用は、「フィルムの種類」、「ガラスのサイズ」、「施工方法」などの要素によって異なります。
基本的には、フィルムが高機能で、ガラスのサイズが大きいほど、防犯フィルム1枚あたりの費用は高くなります。
自分でDIYによってフィルムを貼る場合と、業者に依頼する場合では、人件費が発生しないDIYの方が当然安く済みますが、施工に失敗するとフィルムの買い直しが必要になり、費用も時間も余分にかかるリスクがあるため注意が必要です。
また、フィルム1枚あたりの単価にも注目する必要があります。
業者に依頼する場合、施工枚数が多いと割り引きの対象になる可能性がございます。
自分で貼り付け作業を行う場合に関しては、フィルムの量が多いほど単価が安くなることから、防犯フィルムを貼るガラスの枚数が多いほど窓ガラス1枚あたりにかかるフィルムの単価は安くなると言えるでしょう。
以下では、DIYによって防犯フィルムを自分で貼る場合と、業者に施工を依頼する場合に分けて、おおよその費用相場を紹介します。
自分で窓ガラスに防犯フィルムを貼る場合の費用相場
防犯フィルムのサイズにもよりますが、例えば5平米の窓にフィルムを貼る場合、フィルム代が約5,000円〜20,000円(性能によって変動)、加えて道具代が約3,000円〜10,000円で、合計8,000円〜30,000円程度になります。
防犯フィルムは性能によって価格が大きく異なり、安価な製品では1平米あたり約1,000円程度から販売されています。
より高性能で防犯レベルの高いCPマーク認定品などの場合では、1平米あたり約6,000円~20,000円程度となります。
また、自分でフィルムの貼り付け作業を行う場合は、作業に必要な道具も自分で購入しなければなりません。
例として、養生用のマスキングテープや養生シート、カッターや水溶液を入れるスプレーボトル、ゴムベラやスキージー、汚れがひどい場合はスクレーパーといった道具が必要です。
業者に依頼して防犯フィルムを貼る場合の費用相場
ガラス屋や窓ガラスフィルム専門店などの専門業者に防犯フィルムの貼り付け作業を依頼した場合にかかる費用は、1平米あたり20,000円以上かかることが一般的です。
防犯フィルムの種類や窓ガラスの枚数にもよって変わりますが、複数枚の窓ガラスに施工する場合では、100,000円以上になるケースも少なくありません。
例えば、5平米の窓であれば、施工費用は約100,000円以上になる可能性があります。
防犯フィルムの貼り付け作業を業者に依頼する場合は、DIYに比べるとコストが高くなるというデメリットが気になるという方もおられるかと思います。
ですが、DIYで施工することでコストを大幅に削減できる一方、技術的な難しさや失敗リスクも考慮しなければなりません。
専門業者に依頼すると商品の選定から確実な施工、アフターフォローサービスまで一括して請け負ってもらえるという大きなメリットがあります。
予算と利便性のバランスを考慮して、総合的に判断することが重要です。
防犯フィルムと他の防犯対策の併用
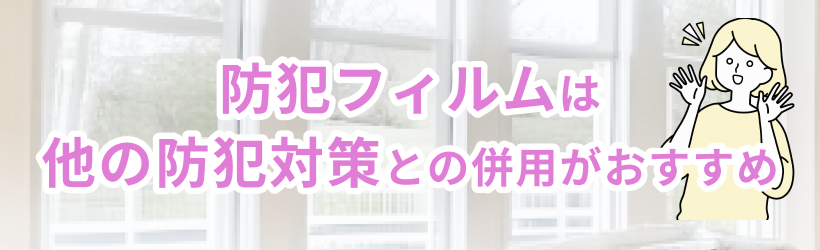
防犯対策として効果的かつおすすめの防犯フィルムですが、より高く安全性を確保するためには、他の防犯グッズと併用することが推奨されています。
以下では、防犯フィルムと併せて使用する際に、おすすめの防犯グッズをご紹介します。
窓用補助錠との組み合わせ
防犯フィルムに加えて、窓用の補助錠を設置することでさらに防犯性が向上します。
窓を侵入経路に選ぶ空き巣などの犯罪者は、クレセント錠の周りのガラスに小さく穴を開けて、カギを解錠してから窓を開けます。
補助錠が設置されていれば、クレセント錠だけでなく補助錠も解錠しなければならないため、窓ガラスを2カ所に分けて破壊するか、ガラスを大きく割る必要がでてきます。
そのため、侵入に時間がかかるだけでなく、作業する姿やガラスを破壊する際に発生する破壊音が目立つ可能性が高くなることから、侵入を諦めさせることができる効果が期待できるのです。
人感センサーライトの設置
窓周辺や玄関に人感センサーライトを設置することで、不審者を寄せ付けない効果があります。
人感センサーライトは人や物の動きや熱を検知したときに、ライトが自動的に点灯して周囲を照らすため、夜間の防犯対策としておすすめであり、近年では広く利用されている防犯アイテムです。
人感センサーライトが点灯することで、空き巣など家屋に浸入しようとする犯罪者に心理的なプレッシャーを与えることができ、犯罪者の存在や侵入しようとしている状況に気付くきっかけにもなります。
また、防犯カメラがある場合は、人感センサーライトの光によって、犯罪時の状況をカラーではっきりとした映像で残すことにもつながります。
オンオフの操作が不要であり、玄関先に人感センサーライトが設置されていれば、夜間の照明代わりとして役に立つというメリットもあります。
防犯カメラとの併用
防犯フィルムとの併用がおすすめの防犯アイテムの中でも、特におすすめとなるのが防犯カメラです。
防犯カメラは設置するメリットは、たくさんあります。
まず、映像での証拠が残ることから、犯罪者の侵入を防ぐ抑止効果が非常に強く期待できるということです。
防犯カメラの種類によっては、アプリ内通知や電子メールでの通知など、設定することで通知機能が使えるものもあります。
ネットワークに接続できる防犯カメラであれば、安定した通信環境を整えることで、リアルタイムにてスマートフォンやタブレットなどから映像を確認することも可能です。
そのため、不法侵入を試みる犯罪者や不審者などを見つけた時には、証拠を残しつつその場ですぐ警察に通報・相談することができます。
防犯用のダミーカメラについて
最近では防犯カメラよりも手軽に導入することができる、防犯用のダミーカメラなども販売されています。
防犯ダミーカメラは本物の防犯カメラそっくりの見た目をしており、人の動きを感知してライトが点滅・点灯する機能を持つ製品などもございます。
ライト付きは電池で動くものが多く、配線の手配やネットワークの接続設定などが不要ですので設置作業も難しくなく、本物の防犯カメラと比較すると導入費用も安価で済ませることが可能です。
犯罪者に対する威嚇としての効果や、けん制効果が期待でき、導入も比較的簡単なことから、防犯カメラの導入が難しい場合などに使用される方も多いようです。
ただし、防犯ダミーカメラは素人の犯罪者には効果があっても、プロの犯罪者は簡単にダミーと見破ることができる可能性が高いため、危険度の高い犯罪者に対しての威嚇効果や犯罪抑止はあまり期待することができません。
また、もしも犯罪被害に遭ってしまった時には、録画機能のない防犯ダミーカメラだと証拠の映像は当然残りませんので、トラブルにきちんと備えたいのであれば、録画機能が搭載されている本物の防犯カメラを設置されることをおすすめいたします。
敷地内に砂利を敷き詰める
防犯用の砂利は、通常の砂利と比較して、砂利の上を歩いた時に大きな音が鳴るように設計・加工されている砂利のことです。
防犯用の砂利が敷き詰められた場所を歩くと、70~85dB程度の音が鳴るため、目立つことを嫌う空き巣や居抜きを狙う侵入犯罪者は避ける傾向にあると言われています。
70~85dBという音量は、セミの鳴き声や電話のベル、電気掃除機が出す音などと同程度であり、快適な生活の妨げになるレベルの音量です。
そのため、敷地内に敷かれている砂利を誰かが踏んで歩いているということが家の中からでも簡単に判断することができ、不審者への威嚇として十分な効果を期待することができます。
砂利に使用される素材はガラスやセラミック、天然石や瓦など様々なものがあり、家の外観や好みに合わせて色味やデザインなどを選ぶことが可能です。
また、一般的な砂利に比べると軽量化されているため取り扱いが簡単で、種類によっては防犯効果だけでなく雑草が生えにくくなる防草効果や、砂利内に含まれている空気による保温効果が期待できる商品もございます。
ただし、防犯用の砂利は重量がなく砕けやすいことから、強い風や豪雨の際には敷地外へ飛ばされてしまったり、砕けて粉塵が発生するといったデメリットがあります。
砂利は固定されていないため足元は不安定で、歩くと沈んでしまうため歩きにくい、転倒したときに破片によって怪我を負いやすいというリスクがある点にも注意が必要です。
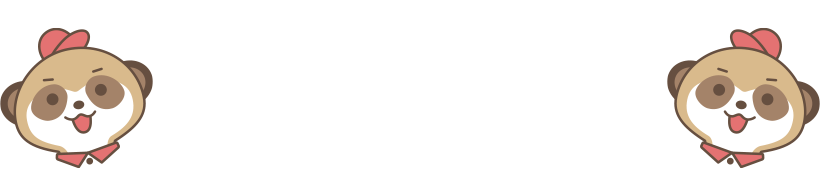
今回は、窓ガラスの防犯性能を向上させる「防犯フィルム」についてご紹介しました。
防犯フィルムは、窓ガラスの防犯対策として非常に高い効果が期待できるアイテムです。
手軽に住宅のセキュリティレベルを高めることができるということ、窓ガラスそのものを防犯合わせガラスにリフォームするより費用を安く抑えることができるというコストパフォーマンスの高さ、人体に有害な紫外線のほとんどをカットする効果があるなど、たくさんの魅力があることから、窓まわりの防犯対策として高い人気があります。
しかし、防犯フィルムは種類や施工方法によって効果や費用が異なることから、適切な商品選び方や正しい貼り付け方を理解しておくことが重要です。
防犯フィルムはDIY作業としてご自身で貼り付け施工を行うことができますが、商品の選定や施工失敗のリスクがあること、時間や手間がかかることには注意するようにしましょう。
防犯フィルムの設置を検討している場合、ガラス屋または窓ガラスフィルム専門家など専門業者のアドバイスを受けることをおすすめいたします。
設置の際の注意点や最適な防犯フィルム選び、商品のメリットとデメリット、料金などついてプロに詳しく相談することで、ご自身の住宅に合った防犯フィルムを安心して導入することができます。
特に、大型の窓や特殊な形状の窓には、高い技術レベルや知識レベルが求められるため、信頼できる業者に依頼することで失敗を防ぐことが可能です。
なお、防犯フィルム単体では完璧な防犯対策にはならないため、窓用補助錠やセンサーライト、防犯カメラなど、他の防犯対策と組み合わせて使用することで、より高い安全性を確保することができます。
ガラス屋ミーアでは、窓ガラスの修理や割れ替えだけでなく、窓用フィルムの施工も承っております。
ガラスフィルムの施工歴は10年以上の業者ですので、お客様が使用されている窓ガラスの種類に合わせた防犯フィルムの選定から施工、アフターフォローサービスまで一貫してサポートすることが可能です。
もし、ご自宅の窓ガラスの防犯性に不安がある方や、今後の安全対策を強化したいとお考えでしたら、ぜひ弊社にて防犯フィルムの設置をご検討してみてください。
お問い合わせはコチラ